プロジェクトの概略
ブラックホールの中は本当に真っ暗で覗けないのでしょうか?
私たちレーザー誘起量子場研究プロジェクトでは、高強度レーザーによってブラックホールの性質とも深く関連する量子的な真空を照らし、その中身を探っていきたいと考えています。
特に最近、量子情報技術の発展に伴い、物理学において「情報」という新しい視点が芽生え、真っ暗で中が見えないと思われていたブラックホールに対する考えも新しい局面を迎えています。素粒子論・量子情報・量子光学・非線形光学・プラズマ物理など幅広い分野の考えを総動員することで、私たちは情報損失問題や量子重力といった未解決・未完な問題や量子情報技術の新しい領域を実験的にアプローチして検証・理解していくことに挑みます。
本プロジェクトは科学研究費学術変革A「極限宇宙」やJST創発的研究支援事業による枠組みも活用して、その研究開発を進めていきます。
メンバー
| 近藤 康太郎 | プロジェクトチーフ |
| 中新 信彦 | 主幹研究員(併任) |
| 吉本 吏貢 | QSTリサーチアシスタント |
| 大澤 悠生 | 実習生 |
| 朝永 真法 | 実習生 |
研究背景と研究内容
・ブラックホールと情報損失問題
アインシュタインが構築した一般相対性理論から光さえ脱出できない事象の地平面をもつ高密度天体のブラックホールの存在が予想されてから100年以上が経ち、最近天体観測では事象の地平面の輪郭の撮影にも成功しています。
そのブラックホールは物質のみならず光も吸い込み、中が見えず全く光らない暗黒の天体のように思われます。つまり、吸い込まれた情報はそのまま失われるように見えます。
一方で、ホーキングは量子論の揺らぎ効果を取り入れ、ブラックホールが事象の地平面近傍で熱放射(ホーキング放射)により光っていると予想しました。現代の視点に基づいたホーキング放射の概念を図1(左)に示します。観測されているブラックホールの重力で引き込まれたことにより周囲のガスが高温プラズマとなって発光する現象やブラックホールの背後の光が重力で曲げられて届いた現象とは異なり、ホーキング放射は事象の地平面近傍を含むブラックホール自身が光るという驚くべき予想でした。しかし、それぞれ真っ暗あるいは光るブラックホールという主張で矛盾しているようにみえます。
これをきっかけに、ブラックホールに吸い込まれた情報は失われるように見えるものの、量子論の観点から情報は保存されているはず、という未解決のパラドックス「情報損失問題」が生じました。この問題は未だ完成していない量子重力理論の構築や注目が高まっている量子情報技術の更なる発展とも深く関わっていると考えられています。
・ホーキング放射と等価原理で結ばれるウンルー効果
ブラックホールの事象の地平面近傍から発生が予想されているホーキング放射は、先の情報損失問題に対する重要な手がかりになりますが、その放射温度は質量つまりブラックホール質量に反比例するため、一般にその温度は宇宙マイクロ波背景放射よりも非常に小さく観測は困難です。
その中で、一般相対論の柱の一つである等価原理(重力場を局所的に打ち消せる座標系が存在する)でホーキング放射と結ばれるウンルー効果があります。ウンルー効果は一見何もないと思われる真空が、一様加速度運動する観測者からは熱放射で光っている場に見える効果のことで、その実験的検証が情報損失問題の解決に重要な役割を果たすと考えられます。その概念図を図1(右)に示します。しかし、ウンルー効果は一般に大きな加速度が必要なことから、ホーキング放射同様にその検証が困難になっています。
・高強度レーザーを用いたウンルー効果の実験的検証
ボース粒子である光子から成るレーザーはエネルギー集中性に優れ、荷電粒子に非常に高い加速度を与えることができます。そのレーザーの中でも関西研が有するJ-KAREN-P(図2)は国内最大で、世界でもトップクラスの高強度レーザーです。しかし、近年レーザーの強度はさらに高くなり、ヨーロッパや中国では出力が10ペタワットになるレーザーを稼働させつつあります。これらに比肩できるよう、私たちは関西研のJ-KAREN-Pの更なる高強度化を進めるとともに、J-KAREN-Pを含めたこれら高強度レーザーを利用し、これまで到達することができなかった高加速度場を実現し、ウンルー効果の検証、ひいては「情報損失問題」の解決に挑んでいきます。
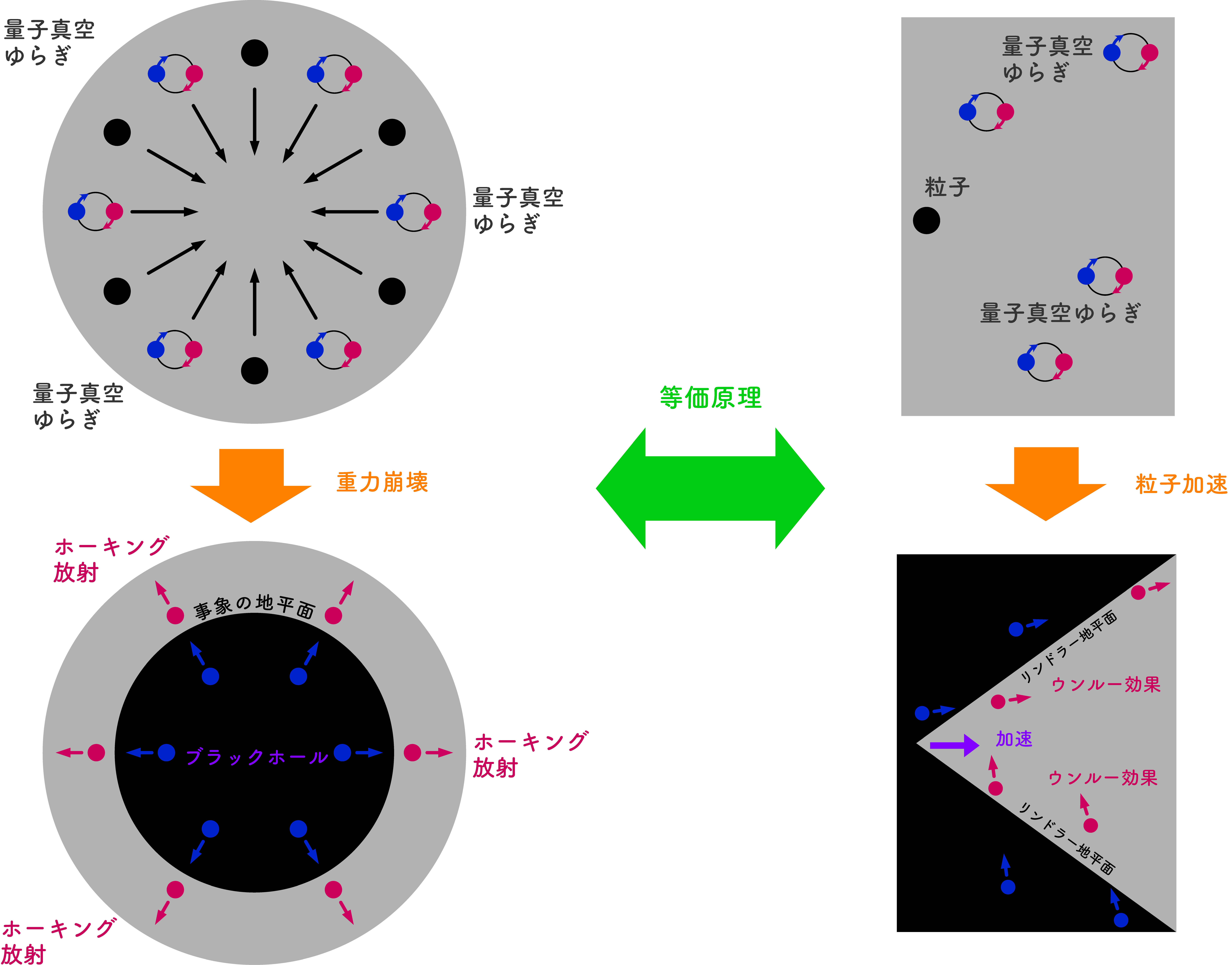
図1: ホーキング放射および等価原理で結ばれるウンルー効果の簡易的イメージ図
左図は重力崩壊による事象の地平面形成時にその地平面を跨る量子効果による真空ゆらぎの片割れ(赤)がホーキング放射として、量子もつれしたパートナーとなる粒子(青)は地平面内に閉じ込められている様子を示しています。右図には等価原理によって結ばれる加速度系における様子を示しています。加速度系においても因果関係を持たない(リンドラー)地平面があり、加速している粒子からは真空ゆらぎの片割れ(赤)しか見えなく、真空が熱放射で光っているように見えるウンルー効果が予想されています。

図2: 国内最大強度を誇るJ-KAREN-Pレーザー


