令和7年4月25日更新
放射線の専門家・指導者養成
1.事故対応に係る専門家養成
1)放射線事故初動セミナー
放射線による被ばくもしくは放射性物質による汚染事象が起きた際の現場での対応、被災者の搬送などについて必要な知識と技能を習得し、各機関での中心的な役割を担える人材を養成することを目的としています。

実習風景:現場での活動の目安を立てるために重要な空間線量率測定、ゾーニングを学びます。

実習風景:研修で学んだことを基に、グループで想定事故現場での対応に取り組みます。
2)国民保護CRテロ初動セミナー
放射線テロ、化学テロ、爆発物テロの事案における初動対応での関係各機関間の活動や役割分担の共通理解、現地調整所での演習・訓練を行うことにより、当該事態対処能力の向上を図ることを目的としています。

実習風景:様々な放射線測定器の使い方について学びます。

机上演習風景:想定事故に対し、機関連携を念頭におき、対応についてグループで討論を行います。
3)放射線災害被ばく医療セミナー
放射性物質による汚染や被ばくを伴う傷病者は、原子力災害以外にも放射性物質を取り扱う医療機関や事業所等での事故やテロで起こりえます。本セミナーは、そのような傷病者の受け入れ及び診療に必要な放射線の基礎的な知識を習得し、適切な放射線管理のもと、診療にあたることができる人材の育成を目的としています。
2.医学利用に係る専門家養成
1)放射線看護課程
放射線診療に関係する看護師が、放射線の人体への影響、放射線の防護、また、放射線診療患者の看護についての基礎知識を習得し、放射線についての理解を深め、放射線に正しく対処することで放射線看護技術の向上を図ることを目的としています。

講義風景:QST病院の医師や看護師から治療や看護の講義を受けます。

実習風景:移動型X線装置を用いて散乱線からの防護について学びます。
2)医学物理コース
医学物理士又は医学物理に興味のある方を主な対象とし、放射線物理や放射線医学の基礎的事項を量子科学技術研究開発機構の特徴を活かした講義を通して短期間で習得することを目的としています。
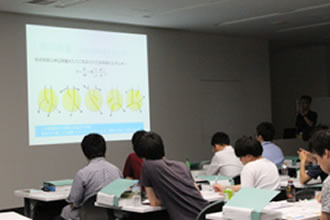
講義風景:様々な分野の専門家から医学物理士に必要な知識を学びます。

見学
3)日本医師会認定産業医制度に基づく生涯研修
産業医が有害業務として電離放射線の取扱いを管理していく際に必要となる、放射線の基礎、労働衛生及び関係法令の知識を習得することを目的としています。
研修への応募はこちら:研修生募集案内
若手人材育成
特設サイトはこちら:実践的に放射線を学ぶ「学生・若手社会人向け4種の研修コース」

放射線の遮へいに関する実習

防護⾐の着脱と体表⾯汚染の測定に関する実習
教育支援
1)出前授業
こどもたちが正しく放射線を理解し、行動・判断できるよう教育支援を目的とし、小・中・高等学校を対象に出前授業を行っています。

授業風景:QSTと中継を結び、自然放射線についての実験をお見せします。

授業風景:こどもたちに放射線測定器で自然の放射線を測定してもらいます。
注)出前授業はWebでの受付は行っていません。
研修への応募はこちら:研修生募集案内
お問い合わせ
下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
放射線医学研究所 共創推進部 人財・交流課
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号
Tel:043-206-3048(ダイヤルイン) Fax:043-251-7819
E-mail:kenshu@qst.go.jp
