平成23年4月22日(金曜日)20時00分更新
平成23年8月24日(火曜日)14時00分更新
1.4月11日に、政府が計画的避難地域というものを指定しましたが、基準になっている20ミリシーベルトの意味について教えてください。
国際放射線防護委員会(ICRP)は専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織ですが、今回の基準は、このICRPの勧告を基に原子力安全委員会の助言を得て定められたと報道されています。
ICRPの2007年勧告では、非常時の放射線の管理基準は、平常時とは異なる基準を用いることとしています。また非常時も、緊急事態期と事故収束後の復旧期を分けて、以下のような目安で防護対策を取ることとしています。
- 平常時:年間1ミリシーベルト以下に抑える
- 緊急事態期:事故による被ばく量が20~100ミリシーベルトを超えないようにする
- 事故収束後の復旧期:年間1~20ミリシーベルトを超えないようにする
現在の福島第一原子力発電所の状況は、2)の緊急事態期に当たります。
今回の国の方針は、緊急事態期の被ばくとして定められている20~100ミリシーベルトの下限値にあたるもので、福島原発周辺の方々の被ばくが、事故による被ばくの総量が100ミリシーベルトを超えることがないような対応をしつつ、将来的には年間1ミリシーベルト以下まで戻すための防護策を講ずることを意味していると思われます。
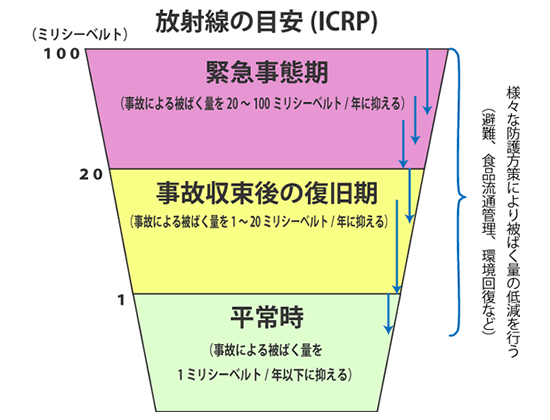
2.計画的避難地域の一部など、福島第一原子力発電所から遠いにもかかわらず、近い地点より空間線量が高い場所が観察されていますが、なぜそのような事が起こるのでしょうか?
チェルノブイリ原子力発電所での事故でも確認されていますように、事故による汚染の程度は事故現場からなだらかに低くなっていくとは限らず、所々に高い地点が見られます。原子力施設で緊急事態が発生し、気体状あるいは粒子状の放射性物質が漏れると、これが大気とともに雲のように流れる状態で移動する場合があります。これを放射性プルームと言います。放射性プルームが上空を通過すると、その地点の空間線量率は一時的に高くなります。またこの放射性プルームは窪地などの地形や風向き、降雨や積雪の影響で降下する場合があり、放射性物質が地表面などに沈着すれば、結果としてその地点の空間線量率が高くなります。このような現象により、事故現場から少し離れた地点に空間線量が高い場所が観察されると考えられています。
3.東京の空間線量は低下する傾向にありますが、一方で長く続いています。東京に住んでいる人の累積の放射線量(3月14日~4月11日の約1ヶ月間)は、およそ何ミリシーベルトですか?
ここでは成人におけるモデルケースについて、体の外から受ける放射線と放射性物質を体の中に取り込むことによって受ける放射線のそれぞれについてお答えします。計算される以下の数値は代表的な放射線量を表し、一人一人については行動や食生活などで大きく違ってきます。
まず大気中の放射性物質によって体の外から受ける放射線量は、文部科学省が発表したデータから累積し、通常時の平均値分を除くと、3月14日以降の約1ヶ月で約16マイクロシーベルトと計算されます(1日8時間屋外に居たとして)。
放射性物質を体の中に取り込むことによって受ける放射線量は水、食べ物、呼吸の3つについて考えます。水道水から受ける放射線量は、1日あたり1.65リットルの水道水を飲んだとして、東京都が発表したデータを用いると約10マイクロシーベルトと計算されます(4.を参照してください)。
食べ物中の放射性物質から受ける放射線量は食事の習慣や量などで個人差が大きく、さらに難しい推定となります。ここでは仮に、1キログラム当たりのヨウ素-131、セシウム-137、セシウム-134の濃度がそれぞれ20、1、1ベクレルの牛乳、それぞれ2、1、1ベクレルの魚、それぞれ150、10、10ベクレルの野菜を約1ヶ月間、毎日食べたとします。これによる放射線量は約69マイクロシーベルトと計算されます。
空気中の放射性物質を吸い込むことによる放射線量は、1日あたり22.2立方メートルの空気を吸ったとして、東京都が発表したちりの中の放射性物質のデータを用いると約21マイクロシーベルトと計算されます。
これらを足しあわせると約1ヶ月間で約120マイクロシーベルトを受けたことになります。この放射線量は、東京-ニューヨーク間を飛行機で往復するときに浴びる放射線量※の上限よりも少なく、健康に影響を与えるレベルではありません。ただし、今後も行政機関からの発表に注意し、要請や指導があった場合にはそれに従ってください。
4.自分が生活する地域の累積の放射線量はどうやって把握したらよいでしょうか?
少し難しいですが、ある程度は計算できます。
まず、大気中の放射性物質から受ける放射線に関しては、文部科学省が発表している事故発生後から現在までの数値を足し合わせることから、およその放射線量を計算できます。以下は、上記(3.)の設問にあった東京の人々における放射線量を算出した場合の例です。
発表された空間線量に照らし合わせた放射線量の計算の例
空間線量について、文部科学省の発表値(3/14~4/11の29日間)は平均0.0927マイクロシーベルト/時でした。
0.0927×24時間×29日=64.5マイクロシーベルト (1)
東京の通常時の平均値は、0.028~0.079マイクロシーベルト/時ですので、その中間値の0.0535を採用し、
0.0535×24時間×29日=37.2マイクロシーベルト (2)
(1)-(2)=27.3 (3)
8時間外出し、16時間は屋内に居たとすると、その分の低減係数は
1×8/24+0.4×16/24=0.6 (4)
受ける放射線量は
(3)x(4)=27.3x0.6=16.38 nearly equal 16マイクロシーベルト
水や食物中に存在する放射性物質からの放射線量の計算の例
次に、水や食物中に存在する放射性物質から受ける放射線量(体内の放射性物質によって将来受ける放射線量を含めた積算値)ですが、これは国際放射線防護委員会による係数を用いて、下記の計算式で推定できます。
受ける放射線量(マイクロシーベルト)=実効線量係数(下の表の値)×放射能濃度(ベクレル/kg)×飲食した量(kg)
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | |
|---|---|---|---|
| 乳児(3ヶ月) | 0.18 | 0.020 | 0.026 |
| 幼児(1-2歳) | 0.18 | 0.012 | 0.016 |
| 子供(3-7歳) | 0.10 | 0.0096 | 0.013 |
| 成人 | 0.022 | 0.013 | 0.019 |
※(経口摂取、ICRP Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the public, CD-ROM,1998を基に放射線医学総合研究所で編集)
水1kgあたりに、ヨウ素-131が8.59Bq(ベクレル)、セシウム-137が0.45Bq、セシウム-134が0.28Bq含まれていると仮定※し、その水を成人が1日1.65リットル、29日間飲んだ場合、それぞれの放射性物質から受ける放射線量は以下のとおりになります。
ヨウ素-131:0.022x8.59x1.65x29=9.0マイクロシーベルト (1)
セシウム-137:0.013x0.45x1.65x29=0.28マイクロシーベルト (2)
セシウム-134:0.019x0.28x1.65x29=0.25マイクロシーベルト (3)
受ける放射線量=(1)+(2)+(3)=9.53 nearly equal 10マイクロシーベルト
※東京都が3/18~4/11に発表した数値の平均値
なお、上記(3.)の試算では、厚生労働省3月19日~4月11日発表の流通品の放射線検査(乳11サンプル、野菜241サンプル、水産物5サンプル)の結果の平均値に近い値を用い、セシウム134と137の合計のみが示されている場合にはその比が1:1であると仮定しています。
空気中に存在する放射性物質から受ける放射線量の計算の例
空気中の放射性物質を吸入することによる放射線量を計算するためには、空気中の放射性物質の濃度が必要です。しかしそのデータはあまり発表されていません。上記(3.)では、東京都労働産業局が公表しているデータを使用し、次のように計算しました。
東京都労働産業局ホームページ
受ける放射線量(マイクロシーベルト)=実効線量係数(下の表の値)×放射能濃度(ベクレル/立法メートル)×呼吸率(ここでは1日当たり22.2立法メートル)×日数
| ヨウ素-131 | ヨウ素-132 | セシウム-137 | セシウム-134 | |
|---|---|---|---|---|
| 乳児(3ヶ月) | 0.072 | 0.0011 | 0.11 | 0.070 |
| 幼児(1-2歳) | 0.072 | 0.00096 | 0.10 | 0.063 |
| 子供(3-7歳) | 0.037 | 0.00045 | 0.070 | 0.041 |
| 成人 | 0.0074 | 0.000094 | 0.039 | 0.021 |
※(粒子状(TypeF)吸入摂取、ICRP Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the Public, CD-ROM, 1998を基に放射線医学総合研究所で編集)
たとえば、東京で空気中のちりの中の放射能濃度がもっとも高かったのは、3月15日の10時から11時の1時間で、この1時間のヨウ素131、ヨウ素132、セシウム137、セシウム134の濃度はそれぞれ、241、281、60、64ベクレル/立法メートルでした。
成人は1日に平均空気22.2立法メートルを吸い込むと言われていますので、この1時間に吸い込んだ放射性物質から将来受ける放射線量の合計の概算値は、以下のとおりになります。
ヨウ素131:0.0074x241x22.2x1/24=1.65マイクロシーベルト (1)
ヨウ素132:0.000094x281x22.2x1/24=0.0244マイクロシーベルト (2)
セシウム137:0.039x60x22.2x1/24=2.16マイクロシーベルト (3)
セシウム134:0.021x64x22.2x1/24=1.24マイクロシーベルト (4)
受ける放射線量=(1)+(2)+(3)+(4)=5.07マイクロシーベルト
このような計算を、すべての時間について行い、合計します。上記(3.)では、3/14~4/11の分を合計しました。蒸気状のヨウ素はここには含まれていません。
なお、子どもの呼吸率としては、1日当たり、乳児(3ヶ月)で2.86立法メートル、幼児(1歳)で5.16立法メートル、子ども(5歳)で8.72立法メートル、子ども(10歳)で15.3立法メートル、子ども(15歳)で20.1立法メートルという数値が、国際放射線防護委員会(Publication 71)から示されています。
このように、事故由来の放射性物質により体外から受ける放射線量と、放射性物質を含む空気の吸入による放射線量、放射性物質を含む水や食物の摂取による放射線量を足し合わせると累積の放射線量をある程度推定することが出来ます。
