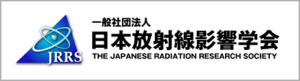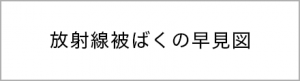<お知らせ> PLANETのこれまでの活動をまとめた論文が国際誌「Journal of Radiation Research」に発表されました(2024年7月)。
PLANETの設立
量子科学技術研究開発機構 (QST)の一部門である放射線医学研究所 (放医研) の使命には、放射線影響研究、放射線防護研究、および原子力災害等に対応した被ばく医療が含まれます。放射線影響研究においては、特に低線量・低線量率の放射線被ばくのリスク推定の不確実性を減少させることが重要な問題として存在します。
この問題の解決へ向けた研究を着実かつ継続的に実施するためには、規制当局を含めた関係者間の連携を促進する、アカデミアや研究機関のオールジャパンネットワークを構築する必要があります。放医研は2016年に、このようなネットワークに関する準備委員会を設置し、準備委員会はネットワークに関する報告書 (添付 [PDFファイル/3.8MB])をまとめました。ネットワークの名称は、放射線リスク・防護研究基盤(Planning and Acting Network for Low Dose Radiation Research、略称PLANET)です。PLANETは、研究ニーズに我が国のポテンシャルを考慮した優先順位を付け、低線量・低線量率の放射線リスクの推定を改善するための戦略を提案します。またPLANETは、国内の関連研究者や研究機関との協力・共同研究の支援体制を提案すると共に、国際機関との連携を推進することも目指しています。
動物実験線量率効果検討ワーキンググループ(WG1)の設置
PLANET運営委員会が2017年に設置され、準備委員会で示された5つの優先的課題を進めることを目的として、具体的な研究課題を検討しています。課題には、低線量・低線量率放射線の健康影響の疫学研究、生物学的機構の解明、動物実験と疫学の橋渡し、年齢・性・遺伝素因・ライフスタイルの修飾効果、およびデータのアーカイブ化が含まれます。運営委員会は、特に動物実験の結果から線量率効果に関する知見を抽出しまとめることを目的として、動物実験線量率効果検討ワーキンググループ (WG1) を設置しました。
WG1の成果1:動物実験データからのDDREFの推定
WG1は、線量率効果係数 (DREF) を推定するために、放医研と環境科学技術研究所から報告された、Cs 137 γ線に慢性的および急性的に被ばくしたB6C3F1雌マウスのがん死亡率データの分析を行いました。被ばく時の年齢によるリスクの違いを考慮したモデルが適用され、急性照射を受けたマウスと比較して、1 日あたり 21 mGyの照射にさらされたマウスにおけるリスクが有意に減少することが示唆されました。その結果、今回の分析条件では、DREFは 1よりも大きくなり、年齢感受性を調整すると約 3 になりました (Doi et al., Radiat. Res., 2020)。
WG1の成果2:低線量率放射線影響実験研究データのレビュー
WG1は、動物モデルでの低線量率影響研究に関する論文のレビューも行っています。疫学データは、ヒト集団の線量・線量率効果係数(DDREF)の推定に大きく貢献してきました。一方、動物モデルを使用した研究は、リスクの大きさやそのメカニズムに関する定性的・定量的データを提供することに大きく貢献しています。このレビューは、がん発生に関連する動物モデル研究について調べ、発がんの根底にある生物学的メカニズムが、放射線による発がんの線量率効果にどのように関与しているのかに注目して知見を整理しています (Suzuki et al., J. Radiat. Res., 2023)。
WG1の成果3:発がんメカニズムを記述する数理モデルを用いたリスク解析
WG1では最近、多段階発がんの数理モデルを用いて、日本の原爆被爆者とマウスの生涯飼育実験から得られた放射線関連がん死亡率データを比較・解析しました。その結果、放射線被曝は、加齢に伴うがんリスクの上昇を時系列的に早期にシフトさせることが示されました。ヒトでは被曝線量当たりの時間シフトが約100倍大きく、これは体細胞突然変異率の動物種差によって説明されることが分かりました。この知見の一般性を確認することで、マウスで得られたデータをヒトのリスク評価により合理的に利用することが可能になると考えられますLINK。(Imaoka et al., Int. J. Cancer, 2024)
研究戦略の改訂と新規ワーキンググループの設立
低線量放射線影響研究分野の国際的な動向と日本の状況を考慮して、2023 年にPLANET は報告書を公表し(LINK)、日本における優先研究分野について、(1) 低線量および低線量率放射線リスクの特徴づけ、(2) 放射線リスクの個別化のために考慮すべき要因、(3) 低線量および低線量率放射線影響の生物学的メカニズム、および (4) 疫学と生物学の統合、にまとめました。PLANETは、これらの研究分野における問題点を更に検討するために、以下の三つのワーキンググループを設置しました。すなわち、さまざまなエンドポイントにおいて影響が報告されている線量および線量率の範囲を特定するための「線量・線量率区分検討ワーキンググループ(WG2)」、さまざまな動物種および臓器の放射線発がんにおける幹細胞の動態の関連性を検討するための「動物種・臓器別線量率効果検討ワーキンググループ(WG3)」、および被ばくから発がんまでのプロセスについて、非変異原性影響に関する研究を含む関連研究を整理し、優先研究分野を特定するための「低線量率発がんプロセス検討ワーキンググループ(WG4)」です。これらのPLANETの活動は、低線量・低線量率放射線リスク評価を改善し、ICRPの次期主勧告の改訂に貢献することを目指しています。
| 甲斐 倫明(主査) | 日本文理大学 |
| 今岡 達彦 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 岩崎 利泰 | 電力中央研究所 |
| 大平 哲也 | 福島県立医科大学 |
| 小林 純也 | 国際医療福祉大学 |
| 酒井 一夫 | 東京医療保健大学、放射線影響協会 |
| 杉原 崇 | 環境科学技術研究所 |
| 鈴木 啓司 | 長崎大学 |
| 田内 広 | 茨城大学 |
| 三角 宗近 | 放射線影響研究所 |
| 保田 浩志 | 広島大学 |
| 吉永 信治 | 広島大学 |
| 鈴木 啓司(主査) | 長崎大学 |
| 今岡 達彦 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 笹谷 めぐみ | 広島大学 |
| 土居 主尚 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 冨田 雅典 | 電力中央研究所 |
| 杉原 崇(主査) | 環境科学技術研究所 |
| 今岡 達彦 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 香田 淳 | 環境科学技術研究所 |
| 笹谷 めぐみ | 広島大学 |
| 田内 広 | 茨城大学 |
| 松本 義久 | 東京工業大学 |
| 保田 浩志 | 広島大学 |
| 鈴木 啓司(主査) | 長崎大学 |
| 飯塚 大輔 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 小嶋 光明 | 大分県立看護科学大学 |
| 臺野 和広 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 中村 麻子 | 茨城大学 |
| 藤通 有希 | 電力中央研究所 |
| 岩崎 利泰(主査) | 電力中央研究所 |
| 大塚 健介 | 電力中央研究所 |
| 小林 純也 | 国際医療福祉大学 |
| 鶴岡 千鶴 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 野田 朝男 | 放射線影響研究所 |
| 廣内 篤久 | 環境科学技術研究所 |
| 山田 裕 | 量子科学技術研究開発機構 |