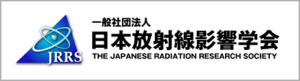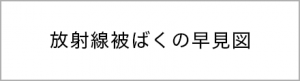(カッコ内に@qst.go.jpをつけたものがメールアドレスです)
今岡 達彦(imaoka.tatsuhiko)
部長。博士(理学)。
専門分野は放射線生物学、乳腺生物学、量子生命科学。放射線による発がんの科学的な仕組み、その基礎にある生体の仕組みを研究し、リスクモデルへの応用を通して放射線防護のために役立つ科学的知見を提供することを目指しています。[researchmap|ResearchGate|ORCID]
王 冰(wang.bing)
遺伝的感受性研究グループ グループリーダー。理学博士。
実験動物モデルを用いて、食習慣が放射線感受性や発がんリスクを変化させるような影響を与えるメカニズムの解明、放射線と心理的ストレスに同時に暴露した際の遺伝毒性やゲノム不安定性への影響の研究、低LET放射線と高LET放射線に対する放射線防護剤の研究開発、低線量・低線量率における放射線影響(適応応答など)の調査、そして高LET放射線の影響に関する研究などを行っています。一方、専門的人材の育成によって、最終的に放射線影響研究や積極的防護、原子力の平和利用(医療利用など)を推進する研究者、管理者、政策立案者による専門集団が形成されることから、人材育成も同様に重要な課題ととらえています。現中長期研究では、マウスモデルを用いて、母親の食習慣が子供の放射線感受性(発がんなど)におよぼす影響、その発生メカニズム、リスク低減化の方法等について研究しています。
森岡 孝満(morioka.takamitsu)
アーカイブ利用・リスクモデル研究グループ グループリーダー。医学博士。
専門分野:放射線病理学・量子病理学・がん予防。研究内容:カロリー制限、カロリー制限の摸倣剤、フィトケミカルおよびエンリッチメント環境などを用いて放 射線に起因するがんの予防研究を行ってます。また、小児期における長期低線量放射線被ばくによる発がんリスクの解明に向け、実験動物を用いた研究 も進めています。
飯塚 大輔(iizuka.daisuke)
老化・炎症研究グループ グループリーダー。博士(獣医学)。
専門分野は放射線発がん、放射線生物学、幹細胞生物学。放射線誘発乳がんメカニズムを明らかにすべく、幹細胞を識別できるようにした特殊なマウスを使い、放射線被ばく後の乳腺細胞の変化を観察することで「がんの芽」 を捉える研究を行っています。その際に、放射線被ばくで引き起こされる早期細胞老化が発がんにどのように作用するかについても明らかにしていきたいと考えています。
臺野 和広(daino.kazuhiro)
バイオマーカー研究グループ グループリーダー。博士(理学)。
専門分野:分子生物学、放射線生物学。研究内容:次世代シークエンサーなどの最新の解析技術を用いて、放射線被ばくに起因するがんのゲノム・エピゲノム異常 の探索と発がんの分子メカニズムについて研究しています。
勝部 孝則(katsube.takanori)
遺伝的感受性研究グループ 上席研究員。理学博士。
専門分野:分子生物学,細胞生物学,放射線生物学。放射線や活性酸素によるDNAの損傷とその修復、放射線の生物影響とその修飾要因に興味があります。
二宮 康晴(ninomiya.yasuharu)
アーカイブ利用・リスクモデル研究グループ 主任研究員。博士(医学)。
腫瘍を移植したマウスを用いて、社会心理ストレスが放射線の影響に、どのような変化を与えるかについて、免疫細胞とがんの成長に着目して解析しています。が んを成長させないような新しいメカニズムを生活習慣要因との関連で探索しています。
尚 奕(shang.yi)
老化・炎症研究グループ 主任研究員。博士(理学)。
マウスを使い、放射線被ばくによる肝癌発生メカニズム及びがん予防研究をしています。
鶴岡 千鶴(tsuruoka.chizuru)
バイオマーカー研究グループ 主任研究員。博士(理学)。
専門分野:放射線生物学。研究内容:放射線誘発のがんと自然に発生するがんを区別できるモデルマウスを使って放射線の種類や被ばく方法の違いによる発がんリ スクの違いを研究しています。そして、なぜ放射線の種類が異なることで “がん”になるリスクが変わるのか?そのメカニズムにも興味があり研究を進めています。
砂押 正章(sunaoshi.masaaki)
老化・炎症研究グループ 主任研究員。博士(理学)。
放射線被ばくによって誘発されるマウスのがんの一つ、胸腺リンパ腫を用いて、発がんメカニズムに関する研究を進めています。特に、被ばくの時の条件(年齢や 遺伝的要因等)が異なることで、がんのでき方がどのように変化するのか?という疑問を明らかにすべく、がんの芽にできる突然変異や、がんができる 途中の組織内の環境に注目した研究に力を入れています。
永田 健斗(nagata.kento)
バイオマーカー研究グループ 主任研究員。博士(生命科学)。
ラット乳腺の放射線発がんに着目し、病理標本作製、幹細胞解析を通じて乳がんの元となる細胞(起源細胞)を特定すべく研究をしています。
甘崎 佳子(amasaki.yoshiko)
アーカイブ利用・リスクモデル研究グループ 研究員。
放射線と発がん性化学物質との複合影響について研究しています。特に、発達期や胎児期の放射線被ばくが、後からばく露した発がん物質よる発がんにどのような影響を及ぼすの かを、マウスを用いた実験から明らかにすることを目指しています。
柿沼 志津子(kakinuma.shizuko)
バイオマーカー研究グループ 客員研究員。薬学博士。
私は放射線生物学と分子生物学を専門としており、放射線発癌、宇宙放射線や放射線療法を含む放射線照射後の腫瘍における放射線特 異的ゲノム変化(放射線シグネチャー)に関心を持っています。放射線の発がんとがん予防のメカニズムにも興味があります。 私たちの研究成果が、一般の人々が放射線を正しく理解するのに役立つことを期待しています。