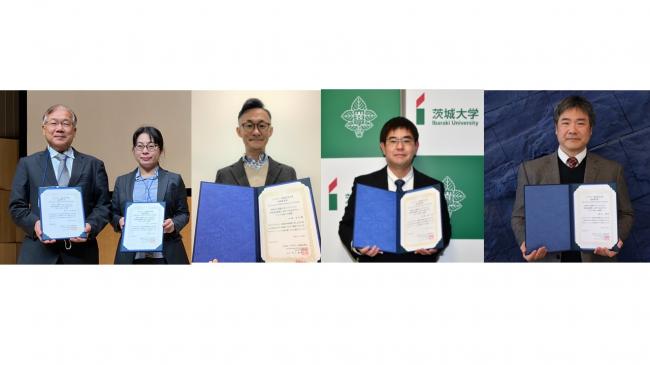第39回プラズマ核融合学会年会 にて「令和4年度第27回技術進歩賞」を受賞
芦川直子(核融合科学研究所), 大塚哲平(近畿大学), 鳥養祐二(茨城大学), 朝倉伸幸(QST, プラズマ理論シミュレーショングループ), 増崎貴(核融合科学研究所)が, 令和4年11月22日-25日に開催された第39回プラズマ核融合学会年会 にて「令和4年度第27回技術進歩賞」を受賞いたしました.
受賞件名
微粒子に蓄積するトリチウムの測定技術開発とJETで生成されたダスト分析ヘの適用
英訳:Development of analytical techniques for tritium remaining in dust particles and application to dust collected in the JET divertor area
受賞内容
受賞者らはイメージングプレート法と電子線プローブマイクロアナライザを利用して,欧州の大型トカマク実験装置JETの炉内において採集され, 日欧BA研究協定のもとQST六ヶ所研究所に輸送された少量(約0.1g)の微粒子(ダスト)に蓄積されているトリチウム量の正確な定量評価,およびそれらを構成する主な元素成分とトリチウム量の関係性を明らかにする技術を世界に先駆けて開発しました.この技術を用いて JET(英国カラム研究所)で 2011 年から開始された ITER Like Wall (ILW) 実験の第 1 期と第 3 期後,および2009年まで実施されたJETの炭素壁実験後にダイバータ領域から採取された微粒子の分析を行い,トリチウム蓄積の特徴を明らかにしました.
核融合炉内のトリチウムインベントリーを評価することは,将来の核融合発電炉を設計する上で必要不可欠であり,特に ITER での炉内トリチウム蓄積予測は,ダイバータの対向材を炭素からタングステン(W) に設計変更するほど重要な問題でした.本分析技術は,シンプルな機器構成でありながら重要な情報が得られた日欧BAにおける原型炉R&D共同研究の成果であるとともに,今後の世界的な展開や将来の核融合発電炉を設計する上で必要不可欠な情報が得られることを期待され,プラズマ核融合学会から「技術進歩賞」をいただきました.
補足:
・プラズマ核融合学会の下記のサイトに掲示されています:
http://www.jspf.or.jp/award2/work.html
・プラズマ核融合学会誌の参考文献:
大塚哲平, 芦川直子, 増崎貴, 朝倉伸幸, 他, 「微粒子のトリチウム蓄積測定技術の開発とJETITER-like Wall実験で生成されたダストへの応用」, プラズマ核融合学会誌 Vol.96 (2020) p.2-5.
http://www.jspf.or.jp/Journal/PDF_JSPF/jspf2020_01/jspf2020_01-02.pdf
参考WEB:
・研究成果はQSTからプレス発表されました(2020年7月1日)
(https://www.qst.go.jp/site/press/41989.html).
・欧州実施機関Fusion For Energy(F4E)のホームページに掲載されました(2020年7月17日)
・日本原子力学会 春の年会にて「2020年度日本原子力学会材料部会Best Figure賞」を受賞いたしました(2021年3月31日)
(https://www.qst.go.jp/site/rokkasyo/49705.html).
研究代表者コメント
この度, プラズマ・核融合学会の第27回技術進歩賞を頂き, 大変嬉しく存じます. この研究は, 2014年から幅広いアプローチ(BA)研究活動の一環として始まり, 日本のLHD(核融合科学研究所), JT-60U(現:量子科学研究開発機構)で培われたダスト粒子への分析手法の確立, およびトリチウムに関する専門家が一堂に会することで, JET装置を有するヨーロッパではなく日本で成しえた素晴らしい成果です. また, この実施については量研機構トリチウムGrの鈴木卓美氏(JAEA出向中), 室舘幸広氏, 川口義彰氏, および茨城大学理学部の大学院生, 菊地絃太氏(現:JAEA), 大和田篤志氏, 欧州側の担当者であるA.Widdowson氏, M.Rubel氏らによる尽力があったことについて, 併せてお礼申し上げます. 研究開発しました手法は, JETのみならずITERや原型炉で発生するダスト粒子に含まれるトリチウムの定量測定にも使用可能です. また, 核融合炉のトリチウムを管理する際には必要不可欠であり, 核融合炉実現に向けた進展の一歩となることを期待いたします.
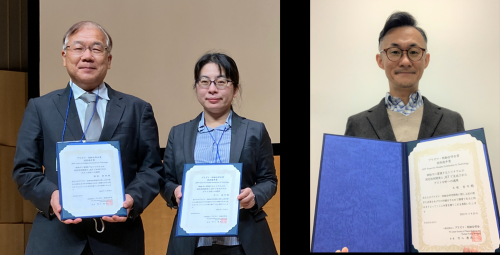
量研担当者:朝倉伸幸, 研究者代表:芦川直子(核融合科学研究所) 研究協力者:大塚哲平(近畿大学)
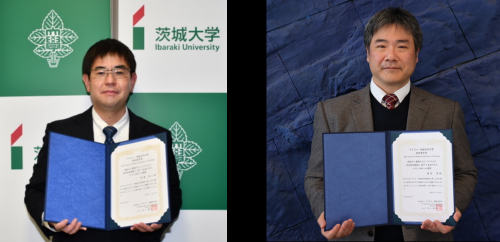
研究協力者:鳥養祐二(茨城大学),増崎貴(核融合科学研究所)