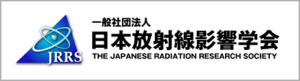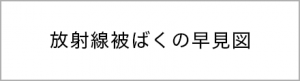2024年12月
- 須田さんが日本量子医科学会第4回学術大会で優秀演題発表賞を受賞しました。LINK
-
2024年11月
-
- 石川主任技術員、森岡グループリーダーの放射線照射動物実験データのデータアーカイブ共通化に関する論文が、Radiation Protection Dosimetryに公表されました。LINK
2024年10月
- QST量子生命科学研究所との共同研究により、ナノ量子センサを使ってラット乳腺の温度を測定することに成功しました。LINK, プレスリリース
- 様々な年齢でガンマ線あるいは中性子線に被ばくしたマウスの白血病死亡リスクを比較し、成体で被ばくした方がリスクが高く、中性子線の強さはガンマ線の高々2倍程度であることを明らかにしました。LINK
2024年9月
- 永田主任研究員が、日本放射線影響学会奨励賞を受賞しました。LINK
- PLANET WG1の事業で発表した総説論文(LINK)が、日本放射線影響学会寺島論文賞を受賞しました。
- 柿沼客員研究員(元部長)が、日本宇宙生物科学会学会賞を受賞しました。
- 永田主任研究員、今岡部長らが、ラット乳腺組織における放射線誘発DNA二本鎖切断生成の感受性は、基底細胞よりも内腔前駆細胞および内腔成熟細胞の方で高いことを明らかにしました 。LINK
- 西村技術員、今岡部長らが、ラット乳がんの分子サブタイプの特徴と放射線被ばくや化学物質曝露との関連性を明らかにしました。LINK
2024年7月
- PLANETのこれまでの活動をまとめ、国際誌「Journal of Radiation Research」に発表しました。LINK
- 山本QSTリサーチアシスタントが、第61回アイソトープ・放射線研究発表会において若手優秀講演賞を受賞しました。LINK
- ホームページを更新しました。
- 今岡達彦が部長に就任しました。
2024年4月
- 鈴木研究員、鶴岡主任研究員、柿沼研究員らが、腸管腫瘍形成モデル ApcMin/+マウスで宇宙飛行士の置かれた状態を再現する実験を行い、模擬微小重力と放射線の複合効果を明らかにしました。LINK
- PLANETの事業において、今岡グループリーダーらが、加齢、がん発生、被ばくの関連性を数理的に解析し、被ばくによるがん死亡早期化のリスクはヒトとマウスで約100倍異なることやそのメカニズムを明らかにしました。LINK
- ホームページを更新しました。
2024年1月
- 「所属学生と卒業生進路」を更新しました。
2023年11月
- 尚主任研究員が、日本放射線影響学会女性研究者顕彰岩崎民子賞を受賞しました。
- 武内実習生、中村QSTリサーチアシスタント、井沢QSTリサーチアシスタントが、日本放射線影響学会第66回大会において優秀演題発表賞を受賞しました。
2023年10月
- 飯塚グループリーダー、臺野上席研究員、石川主任技術員らが広島大学などとの共同で、ApcMin/+マウスにおいて放射線被ばくで生じた小腸腫瘍のメカニズムの一端を明らかにしました。LINK
2023年7月
- 尚主任研究員、森岡グループリーダー、柿沼研究員らが、マウスにおいて脂肪肝と肝細胞がんが放射線によって促進され、カロリー制限によって抑制されることを明らかにした論文を、国際誌「International Journal of Cancer」に発表し、掲載号の表紙に採用されました。LINK
- 井沢大学院生が、アイソトープ・放射線研究発表会第60回大会において若手優秀講演賞を受賞しました。
- 「研究者紹介」を更新しました。
2023年6月
- 仙波大学院生、森岡グループリーダー、柿沼研究員らが遺伝子変異を「読み過ごす」作用を有する薬(アジスロマイシン)で遺伝性の大腸がんを予防することに成功し、国際誌「Biomedicine & Pharmacotherapy」にて報告しました。LINK
2023年5月
2023年4月
- PLANETの活動をまとめた「放射線リスク・防護研究基盤運営委員会報告書」が刊行されました。
- 「研究グループ等紹介」「研究者紹介」「所属学生と卒業生進路」を更新しました。
2023年3月
2023年1月
- 「PLANET」を新設しました。
2022年10月
- 「受託研究」のページを新設しました。
2022年9月
- 天野QSTリサーチアシスタントが、日本宇宙生物科学会第36回大会において発表奨励賞を受賞しました。
- 橘協力研究員が、日本放射線影響学会第65回大会において優秀演題発表賞を受賞しました。
- 山田専門業務員らが、OECD/NEA Topical Groupの一員として、化学物質の毒性評価などへの活用が期待され研究が進んでいるAOP(有害性発現経路:標的分子への作用から有害事象発現に至る経路を、生体の各階層(各臓器、組織、細胞、細胞内器官、その分子等)レベルにおける鍵となるイベントのつながりとして示したもの)の放射線版構築に向けた試みについて報告しました。PubMed
- 今岡グループリーダーらが、低線量率放射線による乳がんのリスクと幹細胞生物学の新たな役割について行った講演のプロシーディング論文が公表されました。PubMed
2022年7月
- 砂押研究員らが、日本科学未来館で行われた「免疫ふしぎ未来2022」にてワクワク免疫実験室(霧箱実験)を実施しました。
- 中村QSTリサーチアシスタント、今岡グループリーダーらが、ヒトに近い病態を示す遺伝性乳がんモデルラットの作製に世界で初めて成功し、日本癌学会の国際誌「Cancer Science」にて報告しました。LINK また、名古屋大学との共同研究で、同ラットが鉄誘発腎がんにも感受性であることを報告しました。PubMed
- 王グループリーダーらが、高LET放射線による子宮内被ばくでの適応応答についての論文が公表されました。LINK
- 森岡グループリーダーが、日本がん予防学会の評議員に選出されました。
- 今岡グループリーダーによる解説記事「中性子線の生物学的影響 ~概説~」が医学物理に掲載されました。LINK
- 橘学振特別研究員が、令和4年東京RBC特別放談会にて講演「放射線によるマウスB細胞性リンパ腫・白血病の 発症メカニズム研究」を行いました。
2022年6月
- 中島徹夫博士、二宮研究員らがマウスを使った実験で高線量率放射線被ばくに対する心理的ストレスの影響を明らかにしました。PubMed
- 鶴岡主任研究員らによる記事「中性子線の発がん影響をマウスで正確に評価」が、Isotope News 2022年6月号に掲載されました。LINK
- 日本放射線影響学会において、今岡グループリーダーが副理事長に、飯塚研究統括が常設委員会委員長に、臺野研究統括が書記に、それぞれ選 任されました。
2022年4月
- 王グループリーダーらが重粒子線の一種である鉄線による骨髄毒性に与える拘束ストレスの影響について明らかにしました。PubMed
- 森岡グループリーダーによる記事「被ばくによる消化管腫瘍に対する予防研究 ーカロリー制限による予防ー」がISOTOPE NEWS 2022年4月号に掲載されました。LINK
- 今岡グループリーダーによる和文総説「ライフステージとDNA損傷応答」が『生体の科学』特集号「DNA修復による生体恒常性の維持」に掲載されまし た。LINK
2022年3月
- 稲葉リサーチアシスタントが修士号、橘学振特別研究員が博士号の学位を取得し、それぞれ各大学から表彰を受けました。
- 橘学振特別研究員らが放射線誘発Bリンパ腫発生メカニズムについて明らかにしました。PubMed
- 西村専門業務員らが放射線誘発乳がんリスクにおける系統差について明らかにしました。PubMed
- 田上グループリーダーらが東北地方で一般的な食用野生植物10種について、集約した移行係数を明らかにしました。PubMed
- 今岡グループリーダーらの放射線誘発乳がんにおける線量率効果と幹細胞生物学の重要性についての総説が採択されました。
- 砂押研究員らが、胸腺における被ばく時年齢依存的な細胞動態を明らかにしました。PubMed
- 今岡グループリーダーが、放射線公衆安全学会第35回講習会にて講演「放射線の人体への影響~情報update~」を行いました。
2022年2月
- 森岡グループリーダーらが東京都立大などとの共同で、エンリッチ環境が消化管上皮細胞の放射線誘発アポトーシス(損傷細胞の除去効果)を 促進することを明らかにしました。PubMed
- 柿沼部長が放射線安全管理研修会(放射線傷害防止中央協議会)で放射線影響研究の進歩というタイトルでセミナーをしました。
- 飯塚研究統括が公益財団法人放射線影響協会放射線影響研究奨励賞を受賞しました。
2022年1月
- 山田専門業務員が、OECD/NEAとの共同で、有害性発現経路に関する作業グループの論文を発表しました。PubMed
2021年12月
- 北海道科学大学等との共同研究で、新生児期の低線量放射線への被ばくがマウスの生殖腺に及ぼす影響を解明しました。PubMed
- 王グループリーダーらが、宇宙放射線にも含まれる低線量鉄イオン線について、食事制限によりその遺伝毒性とゲノム不安定性が軽減できるこ とを明らかにしました。PubMed
2021年10月
- 茨城大学等との共同研究で、エンリッチ飼育環境がDNA修復と免疫能を高めることを解明しました。PubMed
- 国際放射線防護委員会(ICRP)デジタルワークショップで、タスクグループ111の進捗を報告する共同発表に今岡グループリーダーが参 加しました。
2021年9月
- 鶴岡主任研究員が、日本放射線影響学会女性研究者顕彰岩崎民子賞を受賞しました。
- 砂押研究員、橘学振研究員、渡辺QSTリサーチアシスタントが環境科学技術研究所創立30周年記念「放射性核種の環境ダイナミクスと低線 量率放射線の生物影響に関する国際シンポジウム」においてBest Poster Awardを受賞しました。