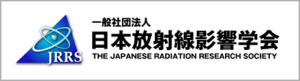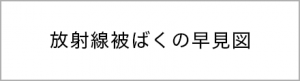放射線医学研究所 放射線影響予防研究部へようこそ
放射線を安全に安心して利用するためには、科学的な根拠に基づいた放射線取り扱いの規制や管理が重要です。そして科学的な根拠を得るためには、どれほどの放射線がどれほどの影響をおよぼすのか定量的に評価し、その仕組みを解明する必要があります。このような研究の重要性は、2011年の福島原発事故を受けて再認識されています。 私たちは、これまでに放射線の様々な生体影響についてマウスやラットを用いて研究し、学術論文として科学的な情報を創出・発信してきました。最近では低線量の被ばくや、子どもと大人の違い、生活習慣の違いなどに着目し、放射線ががんなどの病気のリスクをどのくらい高めるのか、さらにはその予防の可能性も研究しています。今後はこれまでの動物実験等の成果をさらに発展させ、放射線が病気のリスクを高める仕組みを、ゲノム、幹細胞、量子技術などの最新の科学技術を用いて明らかにしていくとともに、これらの知見を疫学調査で得られている知見と統合し、より信頼性の高いリスク評価に役立てていきます。
放射線影響予防研究部 部長 今岡 達彦

What's New
- 2025年12月 須田 QSTリサーチアシスタントが、日本量子医科学会第5回学術大会において優秀発表賞を受賞しました。LINK
- 2025年11月 QST量子医科学研究所との共同研究で、超高線量率炭素イオン線の腸管障害軽減効果が限定的であることを示しました。LINK
- 2025年11月 QST病院との共同研究で、新たな5-ヒドロキシメチルシトシン検出法を開発しました。LINK
- 2025年11月 中村QSTリサーチアシスタント、今岡部長らが、独自開発したBrca1 L63X変異ラットにおいて甲状腺腫瘍の自然発症が増加することを発見しました。LINK
- 2025年9月 柿沼客員研究員、尚主任研究員らの、炭素イオン線によるマウス寿命短縮の年齢及び性依存性を解析した論文が、PLOS Oneに公表されました。LINK
- 2025年8月 中国科学院近代物理研究所等と王グループリーダーらの共同研究により、ミトコンドリアにおける逆電子輸送に関して執筆した招待総説論文が、Biologyに公表されました。LINK
- 2025年8月 臺野グループリーダーらが、放射線被ばくによって発生したがんにおける突然変異の特徴について招待総説論文をBiologyに公表しました。LINK
- 2025年8月 生体の組織間、個体間、動物種間の放射線がんリスクの多様性を考察した今岡部長の論文が、Biology誌の招待総説論文として公表されました。LINK
- 2025年6月 勝部上席研究員、王グループリーダーらが、「胎児期・小児期の栄養環境」が放射線感受性の個人差の一因となることをマウス実験で初めて解明し、Radiation Researchに成果を公表しました。LINK
- 2025年6月 中国科学院近代物理研究所等と王グループリーダーらの共同研究で、インドール誘導体による放射線感受性を解析した論文が、Archives of Biochemistry and Biophysicsに公表されました。LINK
- 2025年5月 ワルシャワ工科大学(ポーランド)と今岡部長らの共同研究で、放射線照射したラットの乳がん発生を物理学的な相転移モデルで解析した成果が、Radiation and Environmental Biophysicsに公表されました。LINK
- 2025年5月 橋本QSTスチューデントリサーチャーが第62回日本放射線腫瘍学会生物部会学術大会で優秀ポスター賞を受賞しました。LINK
- 2025年4月 名古屋大学と今岡部長らの共同研究で、Brca1変異ラットにおける卵巣予備能の低下を明らかにした成果が、Cancer Scienceに公表されました。LINK
- 2025年4月 王グループリーダーらが、チェンマイ大学(タイ)との共同研究で、放射線応答と高脂肪食摂取の関連について招待総説論文を執筆し、Biologyに公表しました。LINK
- 2025年2月 呉工業高等専門学校等と今岡部長、永田主任研究員らの共同研究で、放射線発がんの線量率効果における細胞間の「超競合」の効果を解析した数理モデルの論文が、Radiation Researchに公表されました。LINK